理容・美容・洋菓子といった業界の共通点として「個人店が多い」があります。
最近、これらの業界に異変が起きています。
それは個人店の廃業や倒産が増えていることです。
今回はYahoo!ニュースなどにも取り上げられている記事をもとに「歯科界にも共通して言えること」、「個人の歯科医院は今後どのように生き残り策を考えていけばよいか」を記しました。
なお、生き残り策には具体的に3つの道について記しています。
特に個人医院の院長は、10~20年先を見て院長個人の出口戦略にあった医院運営をしていくことが、将来に渡って安心感をもって経営できることにつながるでしょう。
2019年の理容業・美容業の倒産は過去最多だそうです
2020年1月7日のYahoo!ニュースに【「理容業・美容業」の倒産が急増、過去最多を更新】という以下の記事が掲載されていました。
まず、この記事の内容から一部をご紹介します。
2019年(1-12月)の「理容業・美容業」倒産は、バブル末期の1989年以降の30年間で最多の119件に達した。
これまで過去最多だった2011年の118件を8年ぶりに上回った。件数は2016年の82件から4年連続で増加し、増勢が強まっている。
2019年の理容業の倒産は14件(前年比6.6%減)で前年から1件減少したが、美容業は105件(同10.5%増)と大幅に増加し、明暗を分けた。
また、倒産ではないが、事業停止した休廃業・解散も2018年は317件(前年264件)と増加した。1社で複数店舗を経営しているケースも多く、店舗数ではかなりの数が休廃業・解散で閉店し、一般的な閉店も含めると数千店舗に達する可能性もある。
経営者の高齢化や人材確保などの問題もあり、理・美容業は小・零細規模を中心に淘汰を余儀なくされている。「理容業・美容業」の倒産は、今後も増加する可能性が高まっている。
このように「理容業・美容業」の倒産が増えている背景には
・大都市を中心に店舗が乱立し、過当競争が続く
・人口減少や顧客の高齢化などで、顧客囲い込みが激しさを増す
・1000円カットなど低価格チェーンも台頭し競争が過熱化
が挙げられています。
つまり、理容・美容業は小資本でも独立できる業界のため個人店も多く、既存店舗と新規参入組との間で熾烈な競争が繰り広げられていることが要因でしょう。
そして、この「個人店が多い」「既存店と新規での熾烈な競争」状態は、現在の歯科業界とも似ています。
今後チェーン展開する医院が増えてくると予想されているため、参考になります。
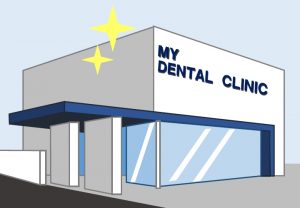
深刻な人手不足などで個人洋菓子店の廃業が増えています
次に、2019年12月16日のYahoo!ニュースの記事【洋菓子店の若手が来ず人手不足、甘くない働き方改革】です。
この記事内容の一部を下記に紹介します。
盛大にオープンした洋菓子店が、数年経つと元の半数以下のスタッフ数で営業しているケースも珍しくなく、仕込みの手が足りないために空白が目立つショーケースもあちこちで見かけるようになった。
以前は稼ぎ頭であったホールケーキも、近年は予約制にして、より生産効率のよい焼き菓子に力を入れる店が増えている。
「新人が来ない」「続かない」「若手を叱れない」というオーナーの苦悩と、増加する個人洋菓子店の廃業。
日本最大の食の総合教育機関である辻調グループの「エコール 辻 東京」創立時から学生を指導してきた喜多村氏は、「学生の『お菓子を作るのが好き』という基本的な姿勢は昔も今も変わっていないものの、就職に関しては時代の変化を感じる」と語る。
「以前は、独立したい、自分の店をもちたい、という学生が多かったですが、近年は、『大好きなお菓子の業界で長く働きたい』という学生が増えているように思います。個人店よりも企業やホテルを希望する生徒が増えているのも、将来を心配してのことでしょう。
『夢はあるけど、不安も大きい』というのが、昨今の学生の特徴かもしれません」(喜多村氏)。
また一方で、現代の若者が孕む弱さにも喜多村氏は言及する。「最近の子は、すごく真面目で、勉強熱心です。
その一方で、YouTubeなどネットでいくらでも情報は拾える上に、現場に出てからも、昔は何年かかけてやっと得られた技術や知識を早い段階で与えられてしまうので、知識があるからこそ、心配性な部分が大きい。いろいろな答えを選べるからこそ、悩んでしまうのです。
また、『働く』ということに対しては、現実的に考えることが弱い部分があるかもしれません」(喜多村氏)。
この記事のポイントとして
・洋菓子専門学校の卒業生の人気就職先は主に企業やホテルで、個人店の就職に中々結びつかない
・最近の傾向としてスタッフは昔ほど独立志向が多くないため、居心地が良ければずっと働く
があります。
人手不足の洋菓子業界で働くスタッフは「大好きなお菓子の業界で長く働きたい」ため、ホテルや企業で働きたいと思う傾向にあるようです。
その結果、個人店にはスタッフが集まらなくなってしまいました。
なかには年間休日を増やし、残業は減らしといった働き方改革を行って、オーナーと個人面談をしっかりと行うことでスタッフの定着率を高めている個人店も増えているようです。
以上が洋菓子業界における個人店廃業の増加ニュースでした。
そしてこの内容は、歯科業界においても下記の点で共通しています。
・個人医院は求人しても応募が益々少なくなっている
・勤務医の中には「開業ではなく居心地が良ければ生涯勤務医でいい」と思っている人が増えている
・スタッフが多い大型医院や分院展開、チェーン展開している医院への就職が増えている
歯科医院以上に厳しいのが洋菓子業界のため、近い将来の歯科業界を反映している記事のように思いました。

また、歯科医院も個人店は売上が伸びにくいだけではなく、収支面からも利益が残りにくい点があることは、以前の記事「1億円で成功」は幻想です!これから開業する先生にとって1億円は最低ラインですにてご紹介しました。
このように、これからは個人店にとって厳しくなる時代ですが、しっかりとしたビジョンをもって運営すれば、過度に心配することもありません。
その理由を次に記します。
個人の歯科医院がこれから10年以上生き残っていく道
ご紹介した記事にあったような理容・美容室、洋菓子店を街の中で見渡してみても、たしかに個人店が多く、その点では歯科医院と酷似しています。
そして、それらの業界で個人店の廃業や倒産が多いといった内容の記事を見ると、歯科医院の院長の中には心配になる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これらの業界と歯科界が異なる点が1つあります。
それは、市場の成長性です。
日本は人口減少時代に入っており、理容・美容業界・洋菓子業界は今のところ業界自体の市場が広がる要素はありません。
そのため、市場も縮小していく中で、個人店の立ち位置は非常に厳しくなっています。
一方、歯科界は予防型を中心に市場が成長していきます。

この点が大きく違います。
そのため、個人店でも存在価値のある医院をつくっていくことができます。
しかし、時流を読まずに、ただ一生懸命頑張ってみても、存在価値を発揮できる医院にはならないでしょう。
というのも、市場が成長するということは参入者も多くなります。
その1つの例が、資本を武器に大規模なチェーン店構想を持って参入してくる歯科医院です。典型例としては、経営と診療の分離がしっかりできていて、スピーディに多店舗化する医院グループです。
このような時代に、個人の歯科医院はどうやって存在価値を見出していくか?
では、個人の歯科医院がこれから生き残っていく道について考えてみます。
といっても、既に開業20年以上が経過して借金もほとんどない医院と、開業して5年以内で大きな借金を抱えている医院では、将来に対する考え方も異なります。
そのためここでは、まだこれから生き残っていく必要がある後者のような開業5年以内の歯科個人医院を対象に考えてみます。
このような個人の歯科医院にとって、生き残りの道は次の3つが考えられます。
1)自ら多店舗化(もしくはチェーン化)していく
(パートナーとなる資本、経営者とタッグを組んで)
2)多店舗化していく医院に(高い価格で)売却できる医院をつくる
3)多店舗化している医院と連携できる医院をつくる
1つずつ、どのようなストーリーになるかをお伝えしていきます。

個人の歯科医院が生き残っていく3つのストーリーを提言します
最初に、
1)自ら多店舗化(もしくはチェーン化)していく(パートナーとなる資本、経営者とタッグを組んで)
です。
これは、医療法人としての規模拡大路線を歩む道です。
予防歯科市場の拡大にあわせながら、予防歯科顧客を起点とした新たな需要を掘り起こすビジネスモデルをつくっていきます。
このケースは歯科医師よりも経営者としての役割の方が多くなり、経営者として予防歯科の普及に貢献し、新しい時代を築く主導者になりたい人に向いています。
またこの場合、大志あるビジョンを描き、リスクが伴っても勇気を持ってチャレンジしていく起業家マインドのある院長である必要があります。
<ポイント>
・規模拡大路線の道を選ぶ院長には大志あるビジョンがないと挫折する
・歯科医師より経営者としての役割の方が多くなるため、予防歯科の普及・主導者となりたい人向き
次に
2)多店舗化していく医院に(高い価格で)売却できる医院をつくる
です。
これは、1)のような医療法人グループに買収される価値のある医院をつくる道です。
というのは、1)のような医療法人も直営だけで拡大していくグループと、M&Aを繰り返して拡大していくグループに分かれるでしょう。
そのため、後者にとって価値の高い医院をつくります。
「脱院長依存、リコール来院者中心、スタッフの定着」を基盤としながら、さらに成長見込みの高い医院づくりです。
なぜこの3つが売却する上で価値をもたらすのか? についてです。
まず「脱院長依存」ですが、院長が中心となって診療も経営も行っている状況では、院長不在になった途端に医院が回らなくなる可能性が高いです。
そのため、診療面では後継者を育成しながら、いざという時のお助け役になり、経営面は権限委譲しながら相談役に回ることで、院長不在でも医院が運営できる医院体質にしていきます。
次に「リコール来院者中心」ですが、同じ患者総数でもリコール来院者の割合が高い医院の方が、売却時の医院価値が今後は高まっていくでしょう。
なぜなら、リコール来院者は口腔内意識も比較的高いため、物販の継続購入や自費診療などにつながりやすいのです。
そのことを経営的にみた場合、1人の患者さんの価値が治療患者よりも高いと判断されるためです。
最後に「スタッフ定着」ですが、これは私が言うまでもなくスタッフが定着しない医院は運営上、リスクが大きく、急に売上ダウンになるリスクを常に抱えることになります。
そのため、スタッフが定着していない医院の価値は下がってしまいます。

これらが買収で広く展開していくグループにとって、魅力となります。
逆に売上は大きくても「自費中心、難しい治療が多い、スタッフが定着しない」医院は、残念ながら魅力的には映りません。
同じ売上でも買収価格は3倍くらい違ってくることもあるでしょう。
そのため、M&Aを展開する医療法人にとって魅力的な医院をつくり、タイミングよく売却できるころも考えながら医院経営をしていきます。
売却後の院長は、売却した医院に一勤務医として働き続けてもよいし、売却益をもとに別の事業をしてもよいし、フリーランス歯科医として、全国の医院を回るのもありな生き方になります。
また、何よりも患者さんが継続して通うことができ、スタッフの雇用も守られることになります。
<ポイント>
・「脱院長依存、リコール来院者中心、スタッフの定着」にするため、5~10年かけて医院を変貌させる努力が必要
最後に
3)多店舗化している医院と連携できる医院をつくる
です。
これは1)のようなグループ医院と連携できる医院づくりをする道です。
1)のようなグループ医院では、できない部分を担当する医院として位置づけます。
例えば、高度な歯周病治療や顎関節症治療などの治療を受け持ち、1)のグループ医院と適宜連携し、得意分野の患者さん向けに力を発揮します。
1)のようなグループ医院にとって難治療の患者さんに自信をもって紹介できる先があることは、1)のグループ医院の患者さんから見た価値向上にもつながります。
また、この医院は複数の1)のようなグループと連携することでリスクを分散させることができます。
そのため、連携可能な医院をつくることを目標とします。
この場合、連携するためのコミュニケーション力が必要になります。
そしてユニット3~4台の歯科医院でも、最も多くの医院さんがこの道を選択されることになると思います。
そのため大型医院にとって「連携しやすい」医院のあり方を模索しながら、準備しておく必要があります。
<ポイント>
・大型医院が取り組まない専門医療分野を突き詰める
・連携をスムーズにするコミュニケーション・関係性づくり
以上、個人の歯科医院がこれから生き残っていく3つの道についてお伝えしました。
1アクション
自身の医院が生き残る道はどれが適当かを、信頼できるパートナーやスタッフと話し合って決める
関連記事
医院承継をスムーズに行う!スタッフ一丸で進む承継の手順があります
あなたの歯科医院の価値を無料で自動算出!医院価値を知って出口戦略をつくりましょう
関連セミナー

承継に対して漠然とした思いはあるものの「テナントだから、借金があるから、人口減の地方都市だから、などの理由で承継できない」と思いこまれている院長は多くいらっしゃいます。
中には「誰にも相談できない」と感じていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでユメオカでは、院長の疑問や不安を解消するため、予防管理型歯科医院の承継に関するセミナーを定期的に開催しています。
基本的にオンラインツールであるZoomを使用したセミナーのため、どこからでも参加できます。また、参加費は無料です。
■現在、定期開催中のセミナー■
【治療型とは価値が違う!予防型歯科医院の承継セミナー】
【閉院予定から第三者承継へ(事例)】
【誰も教えてくれない承継準備を大公開、5年後に引退を決めた58歳院長の事例】
(※)上記は2023年10月現在、申し込み可能なセミナーです。セミナーは今後、追加・変更することもあります。
セミナーの詳細、お申込みはについてはこちらをご確認ください。
【無料】承継相談のご案内

これまで予防に注力してきた予防管理型歯科医院の承継に関する相談は、ユメオカにお問い合わせください。
予防管理型歯科医院について詳しい知識を持たない一般の承継仲介会社は、財務諸表だけを見て売却価格を決定する傾向があります。
しかし実際、予防管理型歯科医院には「リコール数・スタッフの在籍年数・保険自費割合」などの無形価値が多くあります。
ユメオカではその無形価値を評価します。そして「買い手先は見つかるのか?」といった不安にも過去の経験から「貴院が見つかりやすいか否か」もお答えできます。
また、「承継はまだ数年先と考えている」という方には、承継準備に関するサポートも行っております。
承継に関する相談は無料で承っておりますので、お気軽にこちらからお問い合わせください。
その他、ユメオカでは予防型歯科医院経営のマネジメントに関する教材を多数ご提供しております。
教材の詳しい内容・ご購入につきましては、こちらよりご確認ください。
承継LINE@登録
LINE@に友達登録いただきますと、歯科承継の疑問に短く答えたり、最新事例を配信します。
またLINE@から相談でもできるため、承継が気になりはじめた院長は“いざ”という時のためご登録をお願いします。
登録特典としてまして、ユメオカ式 予防管理型歯科医院【承継】のオキテ(PDF形式64P と動画解説)をご提供致します。
問い合わせ
その他、お問い合わせはこちらから受け付けております。
お気軽にご相談ください。


