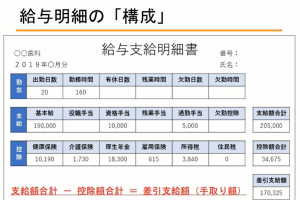Contents
スタッフが2つのグループに分かれている

北海道にある帯広歯科医院(仮名)の院長からの相談です。
医院は開業8年目で、ユニットは現在5台、スタッフは9人います。
この院長には最近、スタッフに関する悩みがあります。
というのも、スタッフが
- Aグループ(古くからいるスタッフによるグループ)
- Bグループ(この1、2年で新しく入ってきたスタッフによるグループ)
と、2つのグループに分かれているのです。
さらに、グループ同士の仲が悪くなっています。
ある日、Bグループのスタッフから院長に相談がありました。
内容は、Aグループのスタッフの行動を指摘するものです。例えば、
☑ミーティング時間に遅れる ☑Bグループのスタッフに対する言い方がきつい
というようなものです。
院長から見ると、たしかにBグループはAグループと比較して、積極的に働いてくれているように思います。
Bグループのスタッフは「Aグループのスタッフに罰を与えてほしい」と院長に言ってきました。
罰の内容は減給や、有給を減らすというものです。
そして院長は悩みました。罰を与えたところで、うまく行くとは思えません。
それよりも罰を与えてしまうことで、かえってAグループとBグループの溝が深くなってしまうんじゃないかと思います。
どうしたらいいものかと悶々と悩む日々が続き、院長はユメオカに相談しました。
チーム・ミッションをスタッフに繰り返し伝えましょう

ユメオカにいただいた相談内容は、「スタッフのグループが分かれている状況で、院長としてどのように対応をすればいいのか」というものでした。
私は、院長に次のような質問をしました。
「院長の理想のチームとは、どのようなものですか?」
これは、医院のあり方につながる質問です。
院長は様々なお話をしてくださいました。端的にまとめると、
スタッフ同士、お互いを尊重し合ってコミュニケーションがとれるチームを作りたい
というものでした。
つまり、これがチーム・ミッションですね。
院長はこのチーム・ミッションを「スタッフ評価するときに一番大切にしたい」と、改めて明確にされました。
そこで私が提案したのは、
チーム・ミッションをスタッフに改めてしっかりと繰り返し伝えていくことで、AチームとBチームの間にある、わだかまりや誤解をなくしていきましょう、というものです。
そしてスタッフに伝える時は、「お互いを尊重し合ってコミュニケーションを取る」では抽象的でわかりにくいので、具体的に、どういう事なのか一つ具体例を挙げて伝えてみては、という提案をしました。
内容は、
☑また、共有する文化を作る
というものです。
例えば、課題をしてこない、言い方がきついというのは行動です。
ですが、このような行動をしたAチームのスタッフには、なにか理由や事情があるかもしれません。
また、言い方がきついなどは、本人自身がそのことに気付いていないということもあります。
そのような行動をとった背景を、「お互いに知ろうとする文化を作っていこう」と院長からスタッフに改めて伝えます。
そのうち、徐々に相手の行動背景を知ろうとする動きがスタッフに浸透していきます。
ユメオカではよくお伝えしていますが、Why – What – How の、Whyの部分です。
この姿勢でチーム・ミッションを支えます。
1回や2回では、なかなか上手くいくものではありませんから、繰り返すことが大事です。
ミーティングを月1回しているのであれば、毎回
チーム・ミッションである「お互い尊重し合って、コミュニケーションをとる」ということに対して、この1ヶ月どんなことを意識したのか
を、まず書き出してもらいます。
それをスタッフ間でシェアします。
そして「お互いにとった行動に対して、その背景を聞いてみる」ことで、徐々に文化ができあがります。
ミーティングだけでなく、朝礼のタイミングもいいですね。
朝礼の場合は時間があまりなく、意識したことを全員が共有するのは難しいので、代表で一人が発表するのを順番に回していくといいでしょう。
クレドを作成してスタッフに行動指針を浸透化しましょう

チーム・ミッションをさらに具体化するためには、行動指針を作ることです。
いわゆる『クレド』と呼ばれるもので、当院の行動指針を10個ぐらいまとめたものです。クレドを作成し見直すことで、スタッフに行動指針を浸透化させていきます。
相手の行動背景を知ろうとし、クレドの浸透を繰り返す中で、徐々にAチームとBチームの誤解や、わだかまりも溶けてくることと思います。
最初は少し遠回りに感じるかもしれませんが、最終的にこの方法にたどり着くかと思います。
スタッフに罰を与えたところで何か変わるわけではないし、チーム間の関係が今より悪化するんじゃないかという院長の懸念はまさにその通りだと言えます。
クレドの例として、ユメオカでは大阪府の「としな歯科医院」様の例をよく出させていただいています。
としな歯科医院のクレドはすごく秀逸なので、参考にしていただければと思います。
1.私たちは、医療人であることを十分認識しております。そのため、患者様の身体の治療だけではなく、心のケアまで考えて思いやりのある行動をします。
2.私たちは、施術者であることを認識し、患者様主体で(受ける側のことを)考えて行動します。そのため「治った」という目安は私たちだけが判断するのではなく、患者様にも判断していただくようにします。
上記のように、としな歯科医院のクレドは、患者さんの背景を理解して取り組めるよう作成されています。
このようなクレドがあることで、「ここに書いてあることは大切なことなんだ」と、スタッフは普段から行動を意識して見直すことができます。
また、これから入ってくるスタッフにも脈々と継がれていきます。
としな歯科医院のクレドは22個ありますが、まずは8~10個程度、作成してみると良いでしょう。
行動指針を作成することで、チームが一丸となっていきます。
関連記事
スタッフにどこまで指示すべき? 「クレド」の浸透でスタッフは院長と同じ方向を向く
関連教材

■『焦らず待てる、任せられる』院長になる!考え方と方法(41分)
「期待し過ぎない・待つ・任せる」ことが大切と頭では理解できていても、実践するには時間がかかります。そこで「新人スタッフがすぐ辞めてしまう」の繰り返しだった医院が、院長の考え方の変化でどのように変わったのか、事例をもとにお伝えしています。
■『空き時間の有効活用でより働きやすい医院へ』(25分)
「キャンセル発生時、スタッフがさぼっているわけじゃないが、して欲しい仕事をしていない」という悩みを持つ医院は多いものです。
職種別に【キャンセル時優先順位業務】リストを作成しておくことで、この問題は解決できます。
こちらはスタッフ10人以上になり、院長がスタッフ1人1人指示できなくなってきた医院向けです。
=======================================================
上記2本を含めた7本のダウンロード教材を現在、提供しています。
動画は短時間でコンパクトにまとめっており、新人スタッフでも理解しやすい内容です。
既に購入されている方は、ぜひ新人教育に役立ててください。
▼スタッフ教育に有効な1本6,600円のダウンロード教材申し込みはこちら http://yumeoka.info/ac_contents
問い合わせ
その他、お問い合わせはこちらから受け付けております。
お気軽にご相談ください。