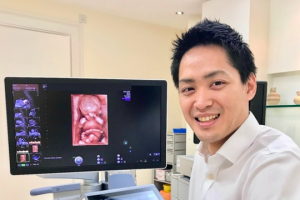その理由は3つあります。
1つ目は2018年発表の国の骨太の方針に「生涯を通じた歯科健診の充実」が明記されたことです。
そして2つ目に、口腔ケア、予防歯科による患者さんの劇的な改善を目の当たりにした医科の先生達が、その大切さを広めてくださる時代になったことです。
3つ目は、予防歯科の定期受診を社員に促すサポートする企業が増えてきていることです。サポートとは例えば、予防歯科を定期受診した社員には年間15,000円を手当として補助するというようにです。
人手不足時代には、社員の健康がより大切になるため、この流れは加速するはずです。そこで、これらの予防歯科の明るい未来を見据えながら、リコール率向上の3つの着眼点をお伝えします
Contents
リコール率向上の3つの着眼点
「治療患者さんは多いが、リコール数が中々増えない」
「リコール率をもっと上げていきたいが、停滞している」
このように悩んでいる院長は少なくありません。ただ、やみくもに「リコール率向上、予防歯科の啓蒙を!」と院内ミーティングで院長が話しても、成果は上がるものではありません。
そしてリコール率向上には3つの着眼点があり、どこから取り組んでいくか? を決めることがまず重要です。
そこで3つの着眼点についてお伝えします。

リコール移行率の向上
これは治療が終わった患者さんがリコールに移行する割合です。
ここで重要なのは医院が患者さんの真の同意なしに、治療が終わった後にリコールの予約をとるのは移行率向上につながりません。
なぜなら、患者さんは「断るのが面倒なのでとりあえず、言われるままに予約をとっておいて、無断キャンセルすればいい」と考えてしまうためです。
このような医院は、初回リコールの無断キャンセル数が多くなります。
そこで大切なのが、ご自身の意志で「予防(リコール)を目的にまず一度、予約をとりたい」と思って初回リコール日を迎える患者さんを増やすことです。
そのために重要なのは、予防歯科の丁寧な説明ではありません。気づきを与えるアプローチです。
それは、患者さん自身が「今までのような治療になったら歯科医院に通う、繰り返し治療のスタイルはもう嫌だな。
定期的に歯科医院に通うのは大変そうだけど、これは自分の将来のためにも必要な習慣だな」という意識をもてるようにすることです。
そしてユメオカでは、治療完了時にこのような気づきを与えるアプローチを【完了比較カウンセリング】という形で体系化しています。
【参考動画】リコール終了後に気づきを与えるアプローチについて
【参考動画】リコールハガキを送る価値の考え方
リコール継続率の向上
これは定期的にリコールに通いはじめた患者さんが、中断することなく通い続けて頂く比率です。
この継続化のために仕組みをつくるポイントはリコール3,4回目の中断をまず少なくすることです。
リコール3,4回目といえば、3カ月リコールであればリコールに通い始めて約1年が経過する頃です。
この頃になるとマンネリ感を感じ始めて「もう、なんとなくもういいかな」ということで中断してしまう患者さんが増える傾向にある時期だからです。

多くの医院でのリコール中断率の統計をとってもこの3,4回が最も高くなりました(関連記事:リコールが継続しない時は来院回数調査をしてみましょう)。
そのためリコール3,4回目はアポ枠を通常より15分程度長くして予約をとります。
そして、その時間にこれまでの口腔内の変化などを写真やグラフを使って共有します。
良くなっているのであれば、それを具体的に患者さんに伝えることで、継続するモチベーションにつながります。
もしくは口腔内の現状維持が続いていれば、予防歯科は現状維持が良いことであるという認識を持っていただくように患者さんにフォローします(ユメオカ参考教材:メインテナンス継続の仕組み)。
またこのタイミングで新しい診療メニューを提案することも効果的です。
それはデンタルエステであったり、90分の自費メインテンテナンスなどです。
なぜなら、リコール3,4回も続けていると自然に初期の頃より口腔内への意識が上がっているため、当初は無関心だった診療メニューにも関心を持てるタイミングになるためです(関連記事:メインテナンスに3、4回通い続ける来院者が継続するための提案)。
【参考動画】リコール中断を防ぐためのエビデンスの使い方
予防歯科目的の初診を増やす
これは文字通りリコールを目的とした初診増です。こういう方が最近は増えています。

5年前には中々、なかった現象です。その背景には雑誌、TV、Webなどの著名なメディアが「予防歯科と全身健康の関係」などをテーマにコンテンツを多くつくっていることがあげられます。
また、医科の先生方が予防歯科の重要性を院内だけでなく、書籍や動画で伝えてくれる時代になっています。
とりわけ認知症、糖尿病や高血圧などの慢性疾患の患者さん向けの専門医の先生達です。
10年前に歯科の先生達が言われていた「お口と全身健康の関係」を今、医科の先生達が伝えてくれる時代に移ってきています。
同じ話を聞くのでも、誰から聞いたかで頭への入り方、気づきは変わります。
例えば、医科の先生による「予防歯科」の話は、患者さんにとって客観性を持って聞こえるのです(関連記事:リコールの必要性を自分ごととして発信してもらう為には医科の先生の声を伝えることでリコール来院者からの口コミが増えます)。
このような背景から予防歯科目的の初診が増えています。
リコール向上の3つの着眼点でした。
【参考動画】初回リコール時は図を使うと、内容が患者さんに伝わりやすい
これからは予防歯科の初診が増える
上記の「予防歯科目的の初診を増やす」で記述しましたようにこれからは予防歯科目的の初診が増える時代になります。
予防型歯科医院にとっては、とてもやりやすい時代になります。
そして予防型歯科医院にとって最も重要なことは、その受け皿をつくっておくことです。
受け皿とはスタッフ、予防歯科の予約枠など物理的なこともそうですが、予防歯科に関心を持ちはじめる人に潜在的な疑問を解決できる情報を発信することです。
歯科以外から予防歯科に関心をもった方々は予防歯科についてどんな疑問をもっているか? を先取りしてその回答を歯科医院側が示します。
その発信は貴院ホームページの予防歯科用ページでも大丈夫ですし、YouTubeで動画発信することでも良いです。
予防歯科に関心を持っている人がどんな疑問を持っているか? についてGoogleの検索されるキーワードで調査しますと現在「費用、メリット、必要性、効果、何歳から、予防歯科専門医院」といったワードです。
これらのワードの内容について答える形で、医院側から情報発信していただくことで受け皿になることができます(関連記事:予防歯科ホームページから予約を増やす為に必要な顧客目線の2つの視点)。
こらから予防歯科に関心を持たれる方向けに、その疑問を入口に丁寧に回答していくことで、予防歯科の習慣がますます広がっていくことにつながります。
1人でも多くの方に予防歯科の大切さんに1日でも早く気づいていただき、後悔のない人生、1日でも多くの充実した人生に貢献できるよう、取り組んでいきましょう。
【参考動画】予防歯科の永続的発展につながるリコールシステム
関連記事