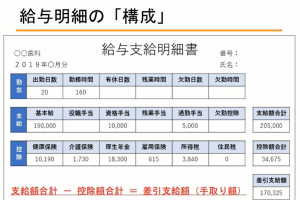予防型にシフトすれば、治療よりもケアに重点が置かれるため、歯科衛生士をはじめスタッフが積極的に動き、患者さんとの関係性を良くしていく努力をしなければ、衰退していくためです。 しかし、スタッフに対しての期待や「して欲しい」ばかりでは、何も変わりません。 そこで、院長自身がどこにフォーカスすればよいかについて記しました。
Contents
スタッフ主導、自律型医院という表現が薄っぺらっく感じた医院見学
2019年5月に埼玉県富士見市にある大月デンタルケア様にユメオカ【予防型経営★実践アカデミー】の院長方15名と訪問し、見学&勉強会を行ってきました。
大月デンタルケアさんは、4フロアありフロア毎にコンセプトが異なる医院づくりをされています。
ユニットは25台程で、スタッフ数は約70名いらっしゃいます。しかし、開業から12,3年間は、ユニット3~4台の診療所でした。
しかし、『地域住民10%の予防定着と女性の活躍の場をつくる』という大義に大月院長が目覚められ、その後10年程で現在のような発展を成し遂げられ、これからさらなる成長を目指す医院さんです。
そして見学当日は午前中に90分、大月晃院長の講話があり、午後から60分で4グループに分かれて医院見学、90分で幹部の歯科衛生士さんによる具体的な医院運営のお話しがあり、そしてグループ討論、交流会を行いました。
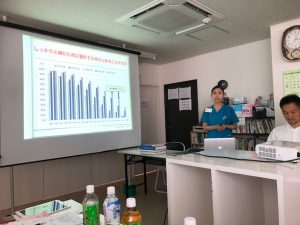
私が最も印象に残っていることは「院長の心の健全性がスタッフ全ての動きに影響することを前提に、院長がご自身と向き合い、スタッフとの関係性を年月をかけて深く築いた」ことです。
大月院長曰く「こちらが心を開いていない状態では、どんなコミットメントも(スタッフに)信用されない」とのこです。
ゆえに「つらいことはつらい」とスタッフに素直に言える勇気が必要ともおしゃっていました。
よく言われる「スタッフ主導の医院」「自立的スタッフのいる医院」という表現が正直、薄っぺらく感じた程、大月デンタルケアさんのスタッフは1人1人が「自分の言葉を使って、自分の責任を背負って」話をされていたのも印象的でした。
院長は「心の安定感」を自ら保とうとするのではなく、周りのサポートを得れば早く進みます
大月デンタルケアさんを見学し院長とスタッフが深くつながっている信頼関係とはこういうことなのかとイメージが持てました(これは実際に見て感じるしか分かりませんね)。
「自分に向き合い、心をオープンにして対話を繰り返す」これは、私を含めて多くの経営者が苦手なことだと思います。
自分の感情を素直に部下であるスタッフに伝えるのは「恥ずかしい」「弱い人間と思われないか」といった気持ちになるためでしょう。
しかし、実際はそうではないことを大月院長は教えてくださいました。
「自分が最終責任をとる覚悟で自分の気持ちを伝える」ことがスタッフの潜在力を引き出すことも、実感しました。
このような院長であれば、スタッフも心をオープンにして、真剣に話をしてきます。しかし、大月院長がそうであるように、そこに至るまでには長い時間がかかります。
その過程には数多くの誤解から、不本意な別れを遂げたスタッフもいることでしょう。
そして、私は多くの成長し続ける院長と接してきて思う彼らの共通点は経営者としての「心の安定感」が維持できていることで、大月院長もしかりです。

その心の安定感を揺るがすことが、2つあります。
それはスタッフとお金に対する漠然とした不安です。
スタッフについては「何を考えているのか、さっぱり分からない」、お金については「この先どうなるのか見通しが見えない」です。この2つが経営者としての院長の心の安定感を奪い取ってきます。
逆に言えば、この2つを解決できる仕組みを持てば、「心が安定する時間」をできるだけ長く保つことができます。
スタッフについてはチーフや外部のブレーンに協力いただくことで解決できますし、お金については専門家に見通しを見せてもらえば、一気に解決します。
それらを最初から1人で行おうとすると、上手くいかず「心の安定感」がどんどん奪われてしまいます。
これら2つとも院長自身の得意分野ではないため、上手くいかなくて当然です。周りのサポートを思い切って借りることで、「漠然とした不安 ⇒ イライラ感 ⇒ 雰囲気が悪くなる」といった悪循環から抜け出せ、そのプロセスを経て大月院長のようにどんどん自ら心をオープンにできるようになっていくのだと私は思います。
関連記事
スタッフが自立的に育つ! 「最高のやりがい」につながる患者さんの声の集め方
▶1エリア1医院のみ、他医院の実践情報を共有する
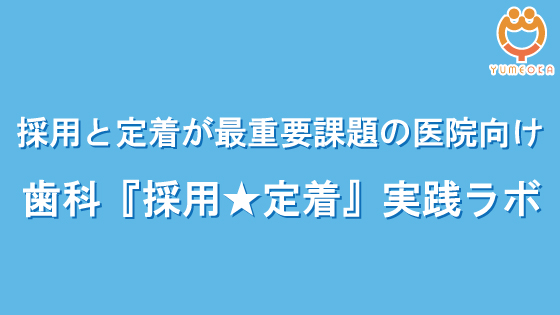
▶「4バランス・医院収支・脱院長依存」など経営教材