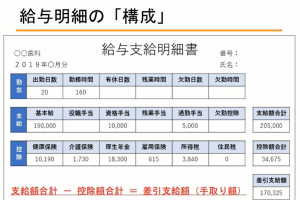この悪循環ループは、医院のエネルギーを放出してしまい、本来の診療に向けるエネルギーまでも吸い取られてしまっています。
そして、このループを抜け出す糸口は既存の考えの延長上からは、残念ながら見出せません。
そこで、この悪循環ループから抜け出すきっかけとなった某医院のストーリーを紹介しながら、その方法について記しました。

Contents
いつも新人スタッフが3か月で辞めてしまう歯科医院
「新しいスタッフを採用できてもすぐに辞めてしまう」この繰り返しになる医院さんの話です。
この医院は名古屋市の中心部で駅から徒歩1分と場所も良いことから、この求人難時代でもスタッフの求人は比較的多くあります。
しかし、歯科衛生士であろうと歯科助手であろうと、新たに採用できても、3~9か月で辞めてしまうことが続いています。
このような状況が続くと求人費用が増えるのはもちろん、院長は「求人会社との面談、面接、入職時の手続き」など採用業務に時間を割かれまた、入職後の新人教育もあり、院長の時間は思った以上に、それらに消費されてしまうことになります。
そのため、診療への影響もでてきます。
この医院で、そこに勤めるスタッフ達に「なぜ、そんなに早いサイクルで新人スタッフが辞めてしまうのか」についての意見を聞いてみました。すると、
✔院長からのプレッシャーが大きくて、居心地が悪くなり、気持ちにも余裕がなくなるみたい
✔そのためか突然、来なくなる新人スタッフも結構多い
といった意見がありました。
そこで普通、新人スタッフはどのような状態かをイメージしてみます。
新人スタッフは未経験者であれば、歯科医院で使われる道具さえ知らないし、例えばスケーリングといった言葉も分からないため、何が何だか分からない状態からスタートします。
経験者であっても、その医院特有のルールや診療システムがあり、とまどいながら、学んでいきます。

一方、院長は未経験の新人スタッフに対して
「分かってはいたけど、何をするにも全然できないな」
「真剣に学んで早く役に立とうという気持ちがあるのかな」
「何もできないなら、少なくとも他スタッフをもっと積極的にサポートしてくれないかな」
と要望が自然に増えてきます。また、経験者の新人スタッフに対しては
「意外と何もできないな、本当に経験ありなのかな」
「さぼっているわけじゃないと思うけど、他にやることあるんじゃない」
というように思ったりもしてしまいます。
このような状況が続くと、院長は無意識にも新人スタッフに対してプレッシャーをかけてしまうことになります。もちろん、院長はプレッシャーをかけているとは微塵にも思っていません。
特に診療が多忙な時間帯にはちょっとしたことで怒りを感じたり、一言、言い過ぎてしまうことにもなります。
診療終了後、「ちょっといい過ぎちゃったかな。意図を誤解されてないかな」と心配になったりもする院長もいることでしょう。
そして、新人スタッフの退職が繰り返されると、院長もさすがに
「自分は人を雇うことには向いてないのかな。知り合いのA先生のようにスタッフを上手くいかして活気ある医院をつくるなんて、自分には到底無理なのかも・・」
と他の先生と比較したりして、自信をなくし落胆してしまいます。
最初からスタッフを上手く活かし、人間関係の良いチームはつくれません
しかし、スタッフ育成をシステム的に行い、1人1人のスタッフの潜在能力を引き出せる院長でも、最初からそうであった院長はほとんどいません。
皆さん、痛い経験を通過しながら、今があるのです。痛い経験と例えば、
・院長を敵視するスタッフが猛威を振るい他スタッフに悪影響を与える
・1人の退職をきっかけに次々と退職する
といったことです。このような経験を通じて
「相手(スタッフ)を変えることではなく、自分(院長)が変わらないとこの悪いループからは抜け出せない」
と気づかれ、自分自身に向き合った結果、院内が大きく変貌していくケースがほとんどです。
その思いの裏には「あんなつらい思いは、もうしたくない。それであれば、これぐらいは我慢した方がましだし、そうしないとまた同じことに・・」がよくあります。
このように最悪のケースを経験してしまったがゆえに、二度とそうならないために、常に自分と向き合わざるを得ない状況まで追い詰められたことが”きっかけ”でしょう。
このような自分改革に気がつかれた院長に私がいつもお伝えするのは
「任せる・待つ・期待し過ぎない」
です。特に新人スタッフに効果的ですが、スタッフ全員に対しても当てはまることです。
これは2016年にアス横浜歯科クリニックの丹谷聖一院長にインタビュー収録を行った時、丹谷先生が言われた言葉です。

そのインタビューでは、この3つを院長が意識するようになって院内が変わってきたという話でした。
また、「最悪のケースを回避できるなら、この3つぐらいはした方がよいと自分に言い聞かせている」といった話でした。
これはとても的を得ていて、私自身も弊社スタッフに対して、今でも経営者として意識している言葉でもあります。そこで、私の経験値と解釈を元にこの3つを説明してみます。
まずは任せる。
成長の可能性を信じて、任せてみることで任された方も任した方も新しい景色が見えてきます。
そして一度、任せたら待つ。
任せた方が「もっと早くできないのか」「なんでまだきないの」と思ってしまうのは実は自然なことです。
しかし、とまどいながら行っている方としては「ミスしてはいけない」といった意識が常に働き、思うように進みません。そのため、任せた方は待つことが重要なのです。
最後に期待し過ぎない。
何事も無意識に期待してしまうと、多くは落胆につながります。
それが感情となって出てしまうと、院内には悪い空気が流れ始めます。
しかし、期待しなければ、落胆する気持ちも湧いてきません。
また、雇っている以上、「期待してしまう」のは普通のことなので、「期待し過ぎない」という方に意識を向けた方がちょうどいいと私は思っています。
この「任せる・待つ・期待し過ぎない」。
ここに医院のあり方を変えていく原点があるのです。

「任せる・待つ・期待しすぎない」を実践する方法があります
といってもこの3つを常に意識し、実践していくのはとても難しいものです。
そこでこれを意識化し、潜在意識に浸透させていくっための実践方法をご紹介します。
1)この言葉を毎日、見えるところに貼っておく
2)最悪のケースを紙に書き出し、それをスマホや毎日見るところに入れておく
3)第三者によるコーチングを受け、この3つの振り返りを毎月行う
4)アンガーマネジメント・セミナーなどを受講する
「任せる・待つ・期待し過ぎない」を紙に大きくかいたり、ポストイットに書いて手帖やパソコンモニターの上側などに貼り毎日、自然にみれるようにしておくことです。
この毎日、自然にみることが潜在意識に刷り込まれていくのに効果的です。

2)最悪のケースを紙に書き出し、それをスマホや毎日見るところに入れておく
これまでの最悪のケース(スタッフの集団退職後の医院など)を紙に箇条書きで書き出し、1)と同じように自然に見れるようにしておきます。
箇条書きにした内容を定期的にみることで原点を振りかえることができます。
3)第三者によるコーチングなどを受け、この3つの振り返りを毎月行う
「任せる・待つ・期待し過ぎない」に対してこの1か月はどのように意識したか? を振り返るクオリティタイムを毎月30分持つ。
普段、意識しようとしていることを毎月、言葉にして表すことで潜在意識への吸収が高まり、やがて習慣化されます。
まずはこの定期的な振り返りを6カ月ほど行ってみます。
4)アンガーマネジメント・セミナーなどを受講する
アンガーマネジメント・セミナーを受講し、自分の怒りの原因を知った上で、この「任せる・待つ・期待し過ぎない」を強く意識すると、より一層、意識化が進みます。
このような方法で実践してみます。1)や2)はスグにでもできることなので、今スグにでも行ってみましょう。明日になったら忘れてしまいますよ(笑)。
今まで色々なセミナーに参加しても効果がなかった医院でも、1年後に振り替えれば、「任せる・待つ・期待し過ぎない」によって、貴院が変わるきっかけになったなと思うはずです。
私自身もそうでしたし、多くのユメオカ・クライアントも同様でした。

きっと、あなたにもできます!
関連記事
スタッフの考えていることが分からない!このような医院向けの解決法があります
信頼できるチーフをはじめて選出したい!そのための選出法、そして育成法があります
関連教材
【人気】新人スタッフが「予防型歯科医院のやりがいに気づける動画(税込6,600円)
動画内のワークでやりがいを考えるきっかけに
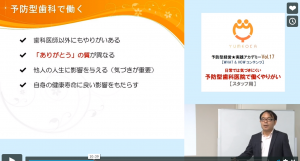
ご注文はこちらです。
▶1エリア1医院のみ、他医院の実践情報を共有する
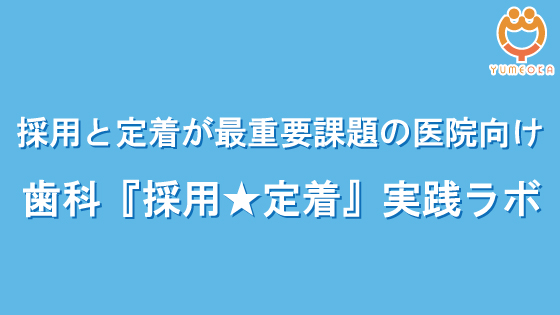
▶「4バランス・医院収支・脱院長依存」など経営教材

問い合わせ
その他、お問い合わせはこちらから受け付けております。
お気軽にご相談ください。